「経理の知識がないけど、一人で会社を経営している...」
「法人化したら、会計処理が複雑になって困っている...」
「本業に集中したいのに、経理作業に時間を取られてしまう...」
このような悩みを持つ一人社長やマイクロ法人の経営者は少なくありません。私もその一人でした。
近年、税金対策や社会保険料の最適化を目的として、フリーランスや個人事業主が法人化するケースが急増しています。私も会社員からフリーランスになり、そして数年前に法人化しました。
しかし法人化すると、青色申告の複式簿記対応や、法人特有の会計処理など、経理の負担が格段に増えます。一人で全てをこなす「一人社長」にとって、この経理業務の効率化は死活問題です。
そこで今回は、マイクロ法人の経営者におすすめの会計ソフト「弥生」について、3年以上使い続けている私の体験をベースに徹底レビューします。簿記の知識がなくても使いこなせる方法や、時間と労力を節約するテクニックをお伝えします。
※この記事には広告が含まれます
目次
マイクロ法人とは?法人化のメリットと課題
マイクロ法人とは、従業員を雇わず、代表者一人で事業を行う小規模な法人のことです。「一人社長」「一人法人」とも呼ばれ、近年急増しています。
統計によると、2020年以降、個人事業主からの法人成りが約20%増加しているというデータもあります。特に、IT業界やコンサルタント、クリエイティブ職など、スキルや知識を提供するビジネスでは法人化の流れが顕著です。
マイクロ法人化の3大メリット
- 税金の最適化:法人税率の活用や、経費計上の幅が広がります。例えば、個人事業主では認められにくい接待交際費や、家賃の一部を経費にできるケースが増えます。
- 社会保険料の節減:役員報酬額の調整により、社会保険料の負担を最適化できます。収入が一定以上ある場合、適切な役員報酬設定で年間50万円以上の節約も可能です。
- 信用力の向上:法人名義の方が取引先からの信頼を得やすく、契約獲得につながりやすいというビジネス上の利点があります。
しかし、法人化には会計処理の負担増加という大きな課題があります。個人事業主の白色申告なら比較的シンプルですが、法人では複式簿記による正確な帳簿作成が必須となります。
私自身、法人化当初は「経理業務に追われて本業の時間が削られる」という事態に陥りました。ところが、適切な会計ソフトを導入することで、この問題を大きく改善できたのです。
一人社長が直面する経理・会計の3つの壁
マイクロ法人の一人社長として、私は以下のような会計の壁に直面しました。多くの一人社長も同様の悩みを抱えているのではないでしょうか。
壁1:複式簿記の複雑さ
私は簿記三級の試験に落ちた経験があるほど、簿記知識に乏しい状態でした。「借方」「貸方」の概念や仕訳の考え方が理解できず、初めての決算書作成時には頭を抱えました。
法人会計では複式簿記が必須ですが、専門知識がないまま始めると、途方に暮れてしまいます。特に「減価償却」や「消費税の処理」など、個人事業主時代にはなかった概念に戸惑いました。
壁2:慢性的な時間不足
一人社長の最大の壁は時間の制約です。営業、制作、顧客対応など本業に集中したいのに、会計処理に貴重な時間を取られてしまいます。
レシートの整理、仕訳入力、請求書作成など、地味な作業の積み重ねが大きな負担になっていたのです。
壁3:税務調査への不安
個人事業主と比べ、法人は税務調査の対象になりやすいというリスクもあります。帳簿の不備や経費計上のミスがあると、追徴課税や加算税のリスクも生じます。
「自分の会計処理は本当に合っているのか?」という不安は常につきまとい、精神的な負担にもなっていました。
一人社長の本音:
「法人化して良かったと思う半面、経理の負担は正直予想以上でした。税理士に全て任せるのも費用がかかるし、かといって自分だけで対応するのも不安...。この板挟み状態をどう解決すべきか悩んでいました」
こうした状況の中で、私が出した結論は『適切な会計ソフトの導入』と『最小限の税理士サポート』の組み合わせでした。そして選んだのが、長年の実績がある「弥生会計」だったのです。
なぜ弥生を選んだのか?簿記知識ゼロでもできた理由
マイクロ法人の会計ソフトとして「弥生」を選んだ理由は、主に以下の3つのポイントがありました。
理由1:フリーランス時代からの継続性
私は個人事業主時代から「弥生の青色申告」を使用していました。法人化後も同じ操作感で使える「弥生会計」に移行できるため、新たに操作方法を学ぶ必要がなかったのです。
システムの継続性は、特に会計初心者にとって大きなメリットです。法人化という大きな変化の中で、少なくともソフトの操作方法で混乱せずに済みました。
理由2:簿記知識がなくても使える直感的な操作性
先述の通り、私は簿記試験に落ちた経験がある会計初心者でした。しかし、弥生会計は「仕訳」という概念を意識せずとも使える設計になっています。
例えば、「経費を計上する」というだけで、システムが自動的に適切な勘定科目に振り分けてくれます。AIによる自動仕訳機能のおかげで、複式簿記の知識がなくても正確な帳簿をつけられるのです。
理由3:税理士との連携のしやすさ
私は日々の経理処理は自分で行い、決算時だけ税理士にサポートを依頼するというハイブリッド方式を採用しています。弥生会計は多くの税理士が対応しているため、データ連携がスムーズでした。
実際、税理士に弥生のデータを渡すだけで、決算処理をしてもらえるため、コミュニケーションコストも最小限で済みます。税理士費用も通常の半額程度に抑えられているのは大きなメリットです。
弥生会計を選んで解決した3つの課題
- 簿記知識がなくても、AIが自動仕訳してくれるので会計処理の難易度が大幅に下がった
- 銀行明細の自動取込や領収書のスマホ撮影機能により、経理作業時間が週6時間→2時間に短縮
- 税理士との連携がスムーズになり、年間の税理士費用を約10万円削減できた
弥生会計の5つの特徴とマイクロ法人向け機能
弥生会計が特にマイクロ法人の一人社長に適している理由を、5つの主要機能から詳しく解説します。実際に3年以上使い込んだ経験から、役立つポイントをお伝えします。
特徴1:AI自動仕訳で簿記知識不要
弥生会計最大の強みは、AI自動仕訳機能です。取引データを入力するだけで、システムが適切な勘定科目に自動で振り分けてくれます。
例えば「コンビニで1,000円の文房具を購入」と入力するだけで、「消耗品費」として適切に仕訳されます。さらに使い続けるほど学習して精度が向上するため、3ヶ月ほど使うと95%以上の精度で仕訳してくれるようになりました。
この機能のおかげで、簿記の知識がなくても正確な帳簿付けが可能になり、専門知識の壁を乗り越えられました。
特徴2:金融機関との自動連携で時短
インターネットバンキングと連携して、取引データを自動取得する機能は特に便利です。主要銀行やクレジットカードに対応しており、手動入力の手間が大幅に削減されます。
私の場合、毎月の200件以上の取引のうち、約85%が自動取込されるようになり、入力作業時間が70%削減されました。この時間短縮効果は一人社長にとって非常に大きな価値があります。
特徴3:モバイル対応で外出先でも処理可能
弥生のクラウド版「やよいの青色申告オンライン」は、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能です。外出先で領収書をスマホで撮影するだけで、データ化して保存できます。
打ち合わせ後すぐに経費精算できるため、「レシートが溜まって整理が大変」という事態を防げます。また、クラウド保存なのでバックアップの心配もなく、PCの故障リスクからも解放されました。
特徴4:豊富なレポート機能で経営判断をサポート
資金繰り表や損益計算書などの財務レポートが自動生成される機能も魅力です。経営状況を視覚的に把握でき、次の一手を考える際の判断材料になります。
特に、毎月のキャッシュフロー推移が一目でわかるグラフは、事業計画の立案に役立ちます。私も四半期ごとにこのレポートを確認して、投資判断や経費削減の検討を行っています。
特徴5:充実したサポート体制
弥生のサポート体制の充実度は特筆すべきポイントです。電話サポートはもちろん、初心者向けのウェビナーやマニュアルが豊富で、困ったときにすぐに解決方法が見つかります。
実際、年末調整の処理方法がわからず問い合わせた際も、丁寧に説明していただけました。「会計初心者をサポートする」という姿勢が徹底しており、安心感が違います。
実際に使って感じたマイクロ法人ならではのメリット
- 役員報酬の設定シミュレーションができるため、社会保険料の最適化に役立つ
- 個人事業主と法人のデータ移行がスムーズで、法人成り後もスムーズに会計処理を継続できる
- 税理士とのデータ共有が簡単で、リモートでの決算処理がスムーズ
他社会計ソフトとの比較
マイクロ法人向け会計ソフトには、弥生以外にも有力な選択肢があります。それぞれの特徴を比較検討し、自分に合ったソフトを選ぶことが重要です。
| 比較項目 | 弥生会計 | freee | マネーフォワード |
|---|---|---|---|
| 初心者の 使いやすさ |
★★★★★ シンプルで直感的な操作性 |
★★★★☆ デザイン性が高く操作しやすい |
★★★★☆ 機能が多く若干複雑 |
| 自動化機能 | ★★★★☆ AI仕訳の精度が高い |
★★★★★ 銀行連携が最も充実 |
★★★★☆ 家計簿連携が強み |
| サポート体制 | ★★★★★ 電話・メール・セミナー充実 |
★★★☆☆ チャットサポート中心 |
★★★★☆ オンラインサポートが充実 |
| 税理士連携 | ★★★★★ 多くの税理士が対応 |
★★★☆☆ 専用税理士ネットワークあり |
★★★★☆ 対応税理士増加中 |
| 実績と 信頼性 |
★★★★★ 350万ユーザー以上の実績 |
★★★★☆ 新興だが急速に成長 |
★★★★☆ 個人利用者が多い |
| 料金 (年間) |
★★★★☆ スタンダード:約25,000円〜 |
★★★☆☆ スタンダード:約36,000円〜 |
★★★★☆ ビジネス:約26,400円〜 |
私が3つのソフトを試して最終的に弥生会計を選んだ決め手は以下の3点でした:
- サポート体制の充実度:会計初心者にとって、困ったときに相談できる環境は非常に重要です。弥生は電話サポートの対応が丁寧で、初心者の質問にも親切に答えてくれました。
- 税理士との連携のしやすさ:多くの税理士が弥生会計に対応しているため、税理士探しや連携がスムーズでした。
- 長年の実績による安定性:30年以上の歴史を持つ弥生は、法改正への対応も迅速で、サービス継続への信頼感がありました。
もちろん、他のソフトにも優れた点はあります。例えばfreeeは銀行連携の自動化において最も進んでおり、マネーフォワードは個人の家計簿との連携が便利です。自分のニーズや優先事項に合わせて選ぶことをおすすめします。
弥生会計を始める方法と初期設定のコツ
弥生会計の導入は意外と簡単です。初めて使う方のために、私の経験に基づいたスタートアップ手順をご紹介します。
ステップ1:無料体験版でお試し
いきなり購入する前に、無料体験版で操作感を確認することをおすすめします。弥生公式サイトから無料体験版をダウンロードして、実際のデータで試すことができます。
私も最初は不安でしたが、体験版で2週間使ってみて「これなら自分でもできる」と確信してから購入しました。
ステップ2:クラウド版かインストール版かを選択
弥生会計には、インターネット経由で利用する「やよいの青色申告オンライン」と、パソコンにインストールする「弥生会計」の2種類があります。
外出先での作業が多い方はクラウド版、自宅やオフィスでじっくり作業する方はインストール版が向いています。私はモバイルワークが多いため、クラウド版を選びました。
ステップ3:初期設定のポイント
弥生会計を始める際の初期設定のコツをいくつかご紹介します:
- 勘定科目の設定:自分のビジネスに合わせた勘定科目を最初に設定しておくと、後の仕訳が楽になります。例えば、頻繁に使う経費項目は、わかりやすい名称にカスタマイズしておきましょう。
- 銀行口座の連携設定:主要な事業用口座は必ず連携設定しておくことで、データ入力の手間が大幅に削減されます。
- 取引先の登録:頻繁に取引する会社は、最初にまとめて登録しておくと入力が効率化されます。
私の場合、これらの初期設定に2〜3時間かけましたが、その後の経理作業がスムーズになり、十分に回収できる時間投資でした。
ステップ4:日常的な経理処理のルーティン化
経理処理を習慣化することも重要です。私が実践している効率的な方法をご紹介します:
- 週1回の更新日を決める:毎週金曜日の夕方1時間だけ、その週の経理処理をまとめて行います。定期的に行うことで溜まらず、作業効率も上がります。
- 領収書はその場でスマホ撮影:外出先で受け取った領収書は、その場でスマホアプリで撮影。紙の領収書を失くすリスクを減らします。
- 四半期ごとのチェック:3ヶ月に一度、税理士に簡単なチェックを依頼。年度末の決算作業を楽にします。
このルーティンのおかげで、経理作業のストレスが大幅に軽減され、本業に集中できる時間が増えました。
:マイクロ法人の経理はソフト選びが大事
一人社長としてマイクロ法人を運営する中で、私が学んだ最大の教訓は「会計ソフト選びが経理の負担を大きく左右する」ということです。
簿記の知識がない私でも、弥生会計のAI自動仕訳や銀行連携機能を活用することで、経理作業時間を70%削減でき、本業に集中できるようになりました。また、税理士との連携もスムーズになり、コスト削減にもつながっています。
マイクロ法人の経理を成功させる3つのポイント
- 自分に合った会計ソフトを選ぶ:操作性、サポート体制、税理士連携のしやすさを重視
- 経理処理を習慣化する:週1回など定期的な更新日を設定し、溜めない仕組みを作る
- 必要に応じて専門家に相談:全て任せるのではなく、自分でできることと専門家に任せることの最適バランスを見つける
弥生会計は30年以上の実績があり、350万以上のユーザーに支持される信頼性の高い会計ソフトです。特に、会計知識が乏しい一人社長やマイクロ法人にとって、その直感的な操作性と充実したサポート体制は大きな味方になるでしょう。
まずは無料体験版で試してみることをおすすめします。実際に使ってみることで、「これなら自分でもできる」という自信につながります。
経理処理に悩む時間を減らし、本業に集中できる環境を整えることで、マイクロ法人としての事業成長を加速させましょう。
※本記事は筆者の実体験に基づいて作成しています。ソフトの機能や料金は変更される可能性がありますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。
法人化の体験記はこちらからご覧ください こんにちは。 データサイエンティストとして活動しているサトシです。 今回は「エンジニア 一人起業」というテーマで、私自身のフリーランスから法人設立に至るまでの体験談をお伝えしていきます。 エンジニアと ... 続きを見る
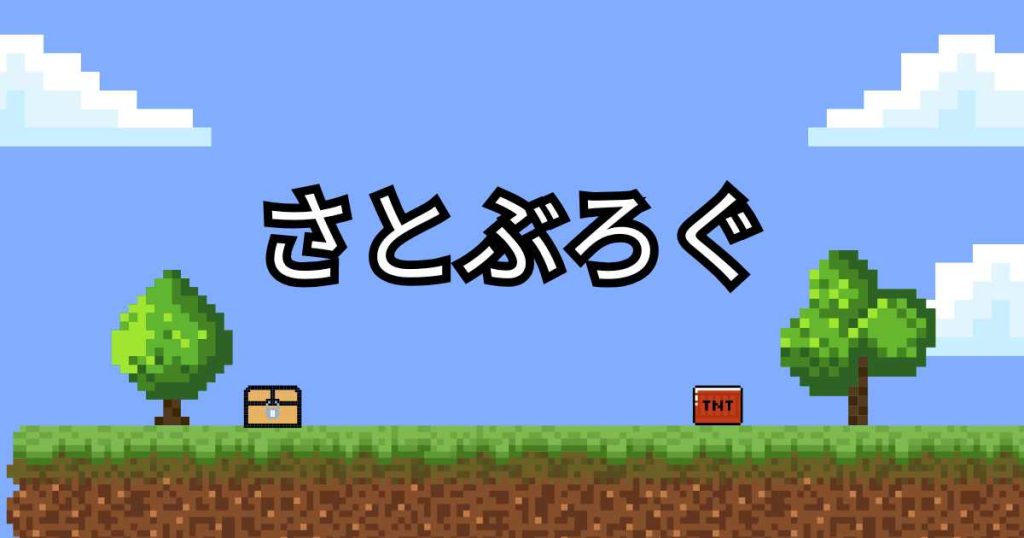
エンジニアの一人起業体験談〜フリーランスから法人化までの道のり
[/st-mybox]